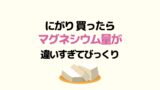塩なんてどれでも一緒、ではなく食べ比べるとすごく味が違うんですよ。例えばうまい! って塩と、辛いだけの塩。
今家で食べるのはゲランドの塩です。ゲランドの塩の味は、塩なのに甘くておいしい!
塩だけを味わって食べ比べると、味の違いが意外にあってびっくりしました。 なので、この記事では塩の味の違いも比較レビューしています。
ゲランドの塩にたどり着くまでには、たくさんの塩を食べ比べましたから、なんです。
そこから塩について調べてみたら。。。たかが塩と言っても。。。
使ってる海水・原料も違うし、製法も違うんですっ
ゲランドの塩の前に食べていた、有名で人気な赤穂の塩・博多の塩・粟国の塩。今回はそれらの塩の違いについて書きます。
塩は人間にとって必須な栄養、絶対に必要なもの。だからこそ知って欲しい事実、日本の塩の歴史! 深すぎてびっくりです。熱く語ってます〜。
塩の栄養
塩に栄養があるなんて、考えたこともなかったですが。。。
栄養・ミネラルのある塩を摂ることは大事。ミネラルは体で作ることができないからなのです。
以前は、安いからとか、CMでやってたから、という理由で選んでた塩です。塩に栄養があるなんて考えたこともなかったから。。。
ただ、ミネラルがない塩もあるので、選び方も重要ですね
ミネラルは体で作れない
塩とは人の体に絶対必要だし、料理にもなくてはならないもの。
ミネラルは、人が生きていくのに必須の栄養ですが、残念なことに自分では作れないのです。思っているより、塩選びは大事かもしれません
塩の重要性について書いてある本もたくさんあります。
精製塩には栄養がない
精製しすぎた塩には、栄養分がない、塩辛いだけだ、と言われますが。。。
でも、塩の栄養といっても、何のことかさっぱりわからなかった。
そして今まで、栄養も味も「これだっ」と思える塩に出会えず、たくさんの種類の塩を試しました。もちろん、塩の栄養についてもサイトで調べたりしながら、結構な種類の塩を食べてきたんだなーと感心します(試して比較することが楽しい性分なので)
以下、今ままでどんな塩を食べてきたか、我が家の塩の歴史(大げさ)を少し紹介です。味レビューと製法についても詳しいです
最初に選んだ赤穂の塩と伯方の塩だった理由は有名だから?
最初の頃、いいんじゃないかと思って選んだ塩は、2種類。
なぜこの2つの塩を選んだのかとその理由は。。。覚えてませーん。笑
赤穂の塩の方は、塩といえば、赤穂が有名でしょ、みたいな? 気がするけれど。
(日本の塩は昔、赤穂で作られてたし、とかの理由で)
ちなみに。。。赤穂の読み方は「あこう」です。
有名な赤穂浪士、年末になったらよくドラマが放送される。。。赤穂浪士🟰あこうろうし、あの「あこう」です。兵庫県赤穂市です 笑
赤穂の塩と伯方の塩の違い
赤穂の塩と伯方の塩、味の違いは粟国の塩やゲランドの塩と比較すると、あまり違いを感じなかったです。製法も少し違うけど、海水は外国ですし。。
ただ、塩の歴史を見ると、どちらも応援したいなあと思います。
1番は塩田が復活されますように。
味の違い
味の違いはほとんど感じられませんでした。どちらも、塩辛い。
粟国の塩や、ミネラルたっぷりのゲランドの塩と比較すると、甘味がない。しおーっからいです。
製法
・赤穂の天塩は、オーストラリアの塩田で天日塩とにがりを作る。その後、赤穂で一部の天日塩を溶かしてからにがりを含ませる。差塩製法。
・伯方の塩は、メキシコとオーストラリアで作った天日塩田塩を瀬戸内海の海水で溶かし、海水のにがりを含む塩を作る。
どこで作られる
どこで作られる、というのが、最終的に販売前の製品となる、という意味なら。。。
・赤穂の塩は兵庫県赤穂市
・伯方の塩は愛媛県今治市伯方町。
ただし赤穂の塩も伯方の塩も、原料の塩は外国産。
原料
・赤穂の塩は、オーストラリアの海水
・伯方の塩は、メキシコとオーストラリアの海水
赤穂の塩とは
赤穂の天塩は赤穂化成という会社が作っています。天海のにがりもあります。
赤穂とはどこの県
赤穂とはどこの県にあるかというと。。兵庫県と岡山県の県境の瀬戸内海に面した都市、赤穂市です。
赤穂市とは、赤穂浪士がいた赤穂市のこと。年末になるとよくドラマ放送される、あの忠臣蔵で有名な赤穂浪士の赤穂です。笑
赤穂化成は濃くて美味しい室戸海洋深層水から作る豆乳も作ってましたが、最近見なくなりました。湯葉もできるぐらいだったので好きだったなあ。
赤穂はあこうと読みますが、赤穂の天塩の読み方がまた難しくて、私ずっと間違ってました。汗
赤穂の塩 読み方は
赤穂の読み方は「あこう」。あかほ、ではありません。
赤穂の塩→あこうのしお、で良いのですが、赤穂の天塩、はどうでしょうか??
実は天塩は。。。
“てんしお”ではなく、”あましお”。
“てんじお”でもなく、”あましお”。
選挙演説みたいに繰り返しますが。。。笑
“赤穂の天塩”の読み方は、”あこうのあましお”が正解です。
味のレビュー
“赤穂の塩”の味はというと。。。
塩、しお、しおーって感じの味です。甘味とか感じません。
伯方の塩とそんなに変わらなかった、という印象しか残ってません。値段は、伯方の塩よりちょっとだけ高め。
赤穂の塩 原料の海水は
赤穂の塩の原材料の海水は、オーストラリア・シャークベイの海水を使っています
世界自然遺産にも登録されている、オーストラリア・シャークベイの、清浄さと豊穣さを兼ね備えた海水
赤穂の天塩HP
赤穂の塩 製法
赤穂の塩の製法は、オーストラリア・シャークベイの海水から作った天日塩を原料に、にがりを含ませて作る差塩製法。
詳しくは↓
江戸時代から、播州赤穂の東浜塩田(ひがしはまえんでん)では「差塩(さしじお)」という”にがり”を多く含ませた塩づくりの手法(差塩製法※)を秘伝としており、当時から「赤穂の塩」として全国に名を馳せていました。
天塩は、この赤穂の「にがりを含んだ塩」づくりを基本姿勢とし、日本食文化が築いてきた伝統の味わいを守り続けています。
※差塩製法・・・濃い海水を煮詰めて塩を取り出す過程で、あえて”にがり”を含ませる(差す)製法。
赤穂の塩HP
赤穂の塩の歴史は江戸時代だった
おーっ、赤穂の塩田は、江戸時代からだったんです。にがり、といえば豆腐作りにも必須だから、古い歴史があるのは当然かもしれません
日本の文化、といえますね
塩田で作れなくなった理由は突然
なんでこうなる。。。体に良いものを作っていたのに。。。効率化という理由だけで、体に良いものを無くしてしまうのは良いことなのか。
まず事実を知って、考えるのも大事
↓赤穂の塩のHPにも、塩田で作れなくなった歴史が書いてありました。
昭和46年、高度成長のまっただ中、政府は「塩業近代化臨時措置法」を国会に提出し、長い歴史をもつ瀬戸内海などでみられた「塩田による製塩法」を廃止し「イオン交換樹脂膜製塩法」による工場大量生産方式を世界で初めて採用実施する方針を明らかにしました。土地と労力を要する塩田を廃止し、効率のみが追求された、高純度の塩化ナトリウム(NaCl)の”サラサラとした白い塩”がつくられました。現存する旧専売公社の「食塩」がそれです。
赤穂の塩HP
日本の塩田の歴史は平安時代から!
日本の塩田の歴史はなんと平安時代から1200年なんですって。それが。。。
たった1つの法律であっという間に無くなっちゃった。
興味ある人は、↑の赤穂の塩のHPの中にある、赤穂の天塩の歴史を読んでみて下さい。ふーむ、と考えさせられる話で、面白かっただけでなく。。。
なんで? とたくさんの人に知って欲しい、考えて欲しい、塩の歴史です。
伯方(はかた)の塩とは
伯方の塩とはどこの県?
伯方の塩の伯方て何のこと? 地名のこと? もしそうならどこにある? と調べたら。。。
伯方とは、愛媛県にありました。愛媛県今治市伯方町でした。
元々、伯方島に塩田があったそうです。
伯方の塩 読み方
伯方の塩の読み方は、はかたのしお、です。
伯方の塩 味レビューと歴史
味のレビュー
味は、塩ーっ、です。けっこう塩辛い、しおーって印象。(何度も言うなっ)
何も他の味は感じませんでした。旨みのようなものも感じられず。
伯方の塩 原料の海水
HPの説明にもあるように。。。
メキシコまたはオーストラリアの塩を、日本の海水に溶かしてろ過し、その塩水から作ってるそうです。
そのためか、値段はリーズナブル。
伯方の塩HPから↓
1997(平成9)年3月「塩専売法」の廃止により海水からの直接製塩が認められ、2002(平成14)年4月からは塩の自由化により原料塩の産地を選択できるようになりましたが、当社は現在もメキシコまたはオーストラリアの天日塩田塩を日本の海水に溶かして、ろ過した後のきれいな塩水を原料にしております。
伯方の塩
伯方の塩 製法
メキシコの塩田に海水を引き込み、2年ほど天日で塩を結晶させる
オーストラリアの海水を引き込み、1年かけて天日で塩を結晶させる
この天日塩田塩には、にがりがほとんど含まれていないので、その後。。。
天日塩田塩を瀬戸内海の海水で完全に溶かし、ろ過したきれいな濃い塩水を原料とすることで海水のにがりを含む塩をつくっています。
伯方の塩HP
伯方の塩が塩田からメキシコ・オーストラリアになった歴史
1971(昭和46)年「塩業近代化臨時措置法」が成立し、日本では「イオン交換膜製塩」以外の方法で海水から直接「塩」を採ることが出来なくなりました。
この様な制約の下、専売公社から許された製塩法は、その当時専売公社が「メキシコ、オーストラリア」から輸入していた「原塩(天日塩田塩)」を利用する方法でした。
塩の歴史 塩田の全廃 伯方塩業のHPより
1971(昭和46)年4月に成立した「塩業近代化臨時措置法」は、塩田を全廃させイオン交換膜製塩に切り替えて、私たち日本人が永年親しんできた塩田塩をなくしてしまうという内容でした。
それに対し、消費者であった松山市在住の有志が、世界で初めてのイオン交換膜製塩(塩化ナトリウム99%以上)に疑問をもち、当時伯方島に残っていた3カ所の流下式塩田の存続運動(自然塩存続運動)に立ち上がりました。
その結果、塩田を残すことは叶いませんでしたが、「自然塩(塩田製塩)を残そう」という消費者運動がきっかけとなり、伯方島で特殊用塩として生産できるようになりました。
伯方の塩HP
そして、この「伯方の塩」という名は伯方島の塩田を復活したいという願いの象徴となってつけられたものであり、登録商標なのです。
伯方の塩の歴史
伯方島の塩田を残せず、やっと伯方で塩を作れるようになっても、↓の規約がひどい
生産上の規約
1973年、厳しい生産上の制約のもと、国から生産販売委託の認可がおりました。
1. 国がメキシコやオーストラリアから輸入していた「原塩(天日塩田塩)」を利用すること。海水から直接塩をつくってはいけない。
2. 平釜(熱効率が悪い釜)を使うこと。
3. 専売塩を誹謗(ひぼう)してはならない。
4. 袋のデザインや文言の変更も専売公社の確認をとること。
日本で塩田を作れないのはなぜなんでしょう
旧専売公社の食塩とは
赤穂の塩のHPに載っていた、この塩↓が気になったので調べてみました。
土地と労力を要する塩田を廃止し、効率のみが追求された、高純度の塩化ナトリウム(NaCl)の”サラサラとした白い塩”がつくられました。
現存する旧専売公社の「食塩」がそれです。
赤穂の塩HPより
Amazonにもあった塩事業センターの塩
旧専売公社の食塩、Amazonで探したら、販売されてます。(ただし、旧専売公社は、名称が変わってます。今の名称は、公益財団法人 塩事業センター)
この塩は、ミネラル分・栄養がない塩なんですよね。。。その分安いけど。
この塩は体に悪いと言われている塩ですね。
そもそも、イオン交換法で精製されすぎた、純度の高い塩化ナトリウム(NaCl)は工業用という話もあります。調べてみてください
↓のビンは可愛い。(10本は多すぎる)
今は、塩は国内で自由に作れて、自由に輸入できますが。。。それ迄は、塩にはいろいろな歴史があったんだなぁ、と思わせる、効率化を追求した塩。栄養やミネラルでは選べない塩です
粟国の塩
で、我が家は、伯方の塩・赤穂の塩をやめた後。。。粟国の塩を長い間使ってました。
粟国の塩とは、どこの県
粟国とはどこの県にあるかというと、沖縄県です。沖縄県粟国島。
粟国島って、スキューバダイビングでも有名で、ギンガメアジやイソマグロの群れもいます。冬にはハンマーヘッドシャークが見れる素敵な海の島で、海の透明度が素晴らしいです。
粟国の塩 味レビュー 赤穂の塩・伯方の塩と比較
粟国の塩の味は。。。
伯方の塩、赤穂の塩と比較すると、粟国の塩の方が塩味がソフトな感じ。ただ粟国の塩も、けっこう塩辛いです。(後で紹介するゲランドの塩は甘味があるけど)
でも塩味がきつめっていうのは、わかる気がします。海によって塩分濃度が違うからです。
日本と海外で海水浴した時を比べると、海水の味が違う、と思ったことがあります。沖縄の海水は、確かに味が濃いというか、塩辛く感じました。
陸地のミネラル分の出方によるのかな?本当のところはどうなんでしょうか。
それでも、伯方の塩や赤穂の塩、と味を比較すると。。。粟国の塩の方が旨味分が多い、と感じました。(その分値段も少し高い)
粟国の塩 原料の海水
粟国の塩の原料は、沖縄県粟国島でポンプで汲み上げた海水です
粟国の塩 製法
粟国の塩の作り方は、面白かった。上から吊るした竹に塩水をポタポタ落として作るんですね。詳しい作り方は、粟国の塩のHPに載ってて面白いです。
ポンプで海水を吸い上げ、穴あきブロックを四方に積み上げた、高さ10mの建物「採かんタワー」に通します。
タワー内には竹が約1万5千本つるされており、汲み上げた海水を何度も竹に流して循環させ、1週間以上かけて塩分濃度約6倍~7倍(塩分20%前後)に濃縮したかん水を作ります。
粟国の塩HP
今使ってるのはゲランドの塩
何年もこの粟国の塩をずーっと使ってたんです。満足してましたから。
でも、ゲランドの塩を使い出してからは。。。ゲランドの塩一筋です。もう戻れない。
ゲランドの塩は甘い。塩だけど
ゲランドの塩は、塩だけど、甘い。いや正確に言うと、甘味のある塩味。美味しいーと思える塩。
これがミネラルの力?なのかもしれないと思って食べてます。
そしてゲランドの塩は、黒っぽいです。
↓にがりも比較で違いにビックリ